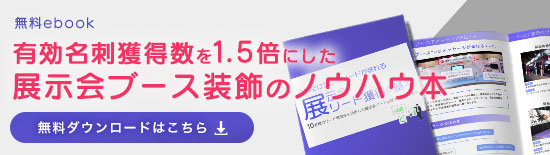展示会動画とは?|制作メリットや活用事例、制作方法まで解説
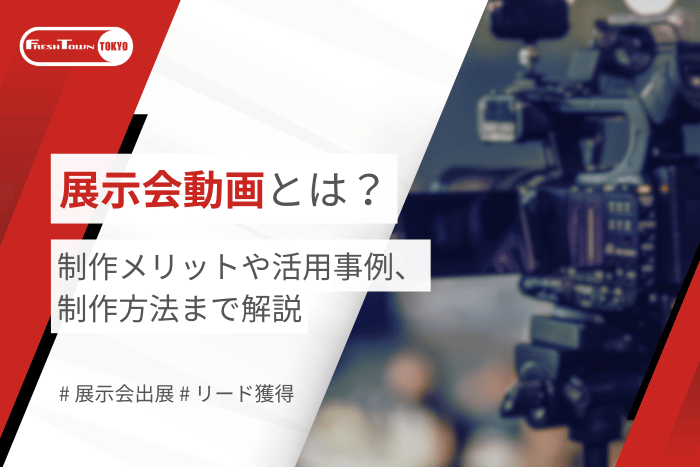
展示会におけるマーケティングは、限られた時間の中で多くの来場者に自社の魅力を伝え、製品やサービスへの興味・関心を喚起することが求められます。その中でも、動画は視覚・聴覚に訴える表現手法として注目を集めています。
近年では、静的なディスプレイや写真、テキストによる説明に加え、映像によって動きや演出、音響を効果的に組み合わせることで、インパクトのあるプレゼンテーションが可能となっています。特に、ブースに設置されたモニターでの映像再生や、オンライン配信を組み合わせたイベントでは、その効果がさらに高まっています。
本記事では、展示会動画の活用メリットや制作のポイント、よく使われる種類、参考となる事例まで、徹底的に解説します。また、制作会社選びや依頼の流れ、費用の目安も紹介しますので、展示会に向けた映像活用を検討中の企業担当者の方はぜひ参考にしてください。
目次
展示会動画のメリットと役割とは
展示会動画は、来場者に強く印象を残し、限られた時間で多くの情報を届ける手段として有効です。展示会という環境では、企業が製品やサービスの魅力を伝える時間は非常に短く、周囲のブースやディスプレイとの競争も激しいため、視覚的に訴える映像コンテンツの導入が欠かせません。
具体的には、以下のようなメリットがあります。
・ 視覚・聴覚に訴えかけ、記憶に残りやすい
・ 情報量の多い内容でも、短時間でわかりやすく伝えられる
・ 商品紹介やサービスの価値を直感的に訴求できる
・ 企業のブランドイメージやコンセプトを統一感を持って演出できる
・ オンライン施策と連動し、SNSやYouTubeなど他の媒体での再利用が可能
また、営業活動の一環として、動画を視聴した来場者との商談化率を高める効果も期待できます。PRやプロモーションのツールとしても優秀で、展示会場での注目を集めるだけでなく、イベント終了後のフォローアップにも活用できるのが特徴です。
来場者の注目を集める映像の力
展示会会場では、多くの企業が独自の映像やプレゼンテーションを展開しており、その中で差別化を図るためには、来場者の視線を引きつける強い演出やインパクトが重要です。たとえば、アニメーションやCGを使ったダイナミックな映像、BGMやナレーションで臨場感を与える工夫が挙げられます。
さらに、テロップや字幕を適切に配置することで、雑踏の中でも内容を理解しやすくなり、音が聞こえにくい会場環境にも対応できます。また、構成を工夫することで、視聴者の注意を自然に誘導し、製品やサービスの魅力を段階的に伝えることができます。
映像の導入によって、来場者の足を止め、ブースでの体験を強く印象づけることができれば、最終的な商談や顧客獲得にもつながります。これらのことから、展示会動画は単なる紹介ツールにとどまらず、マーケティング戦略の核とも言える存在です。
展示会で活用される動画の種類と特徴
展示会で使用される動画にはさまざまな種類があり、それぞれに適した使い方と役割があります。代表的なものとしては、実写映像、アニメーション、CG、インタビュー、商品紹介などが挙げられます。展示会の目的やブースの規模、訴求したい内容に応じて、最適なタイプを選ぶことが重要です。
以下は、主な動画の種類とその特徴です。
・ 実写動画:製品の使用方法や導入事例などをリアルに伝えることができ、
信頼感や現実感を与える
・ アニメーション動画:複雑な仕組みやサービスの流れを視覚的に表現しやすく、
理解を促進する
・ CG動画:製品の内部構造や未来的な演出をダイナミックに見せることで注目を集めやすい
・ インタビュー動画:顧客の声や担当者のコメントを通じて、実績や信頼性を訴求
・ 商品紹介動画:製品の特徴やメリットを短時間で伝えられるため、集客と営業に直結しやすい
各動画の長さやデザイン、表現方法は、視聴者の視線を意識した構成にすることで、より効果的なプレゼンテーションが実現できます。
実写・アニメーションの使い分けと演出効果
実写とアニメーションは、どちらも効果的な映像手法ですが、それぞれに適したシーンや目的があります。実写は、製品のリアルな質感や使用シーンを伝えたい場合に向いています。たとえば、現場での使用風景や操作方法のデモンストレーションなどは、実写による表現が最適です。
一方、アニメーションは、複雑な製品の構造や仕組みを視覚的に説明したい場合や、まだ実物が存在しないサービスやソリューションの紹介に適しています。イラストや図解を動かすことで、難解な内容も視覚的にわかりやすく伝えることができます。
さらに、両者を組み合わせた「ハイブリッド動画」も有効です。実写によるリアルな質感と、アニメーションによる情報補足を同時に行うことで、視覚的にも飽きず、情報伝達力の高い映像になります。
演出面では、BGMやナレーション、テロップ、字幕などを効果的に用いることで、視聴者の理解と記憶への定着を促進します。展示会という多くの情報が飛び交う場では、こうした工夫が他社との差別化につながります。
効果的な展示会動画制作のポイント
展示会動画を制作する際は、ただ映像を作成するだけでは十分とは言えません。視聴者の心を動かし、自社の製品やサービスへの理解を深めてもらうためには、構成や演出に細やかな配慮が必要です。
まず重要なのは、「誰に何を伝えたいのか」という目的を明確にすることです。企業のブランディングを意識した映像にするのか、製品機能の紹介に特化した内容にするのかによって、構成や表現の方向性が大きく異なります。
次に意識すべきは、来場者の滞在時間が限られているという前提です。そのため、動画の長さは1〜3分程度のコンパクトなものが望ましく、最初の数秒でインパクトを与え、視聴を引きつける必要があります。
また、制作における工程は以下のように整理できます。
1. 企画:目的・ターゲットの明確化、伝えるべき内容の精査
2. 構成案作成:ストーリーボードやナレーション台本の設計
3. 撮影・作成:実写またはアニメーションによる映像制作
4. 編集:演出、エフェクト追加、音声調整など
5. 確認・修正:社内チェックやクライアントとのすり合わせ
6. 納品:各媒体に最適化したファイル形式で出力
こうした制作プロセスを踏むことで、効果的な映像が完成します。
商品紹介に効果的なテロップ・音響・情報量の工夫
商品紹介動画においては、テロップや字幕の活用が欠かせません。展示会の会場は騒がしく、音声だけでは情報を正確に伝えられないことが多いため、視覚的な情報補足が求められます。
特に、以下のような点が有効です。
・ 製品のスペックや特徴を文字で表示し、視認性を高める
・ BGMや効果音を使って雰囲気や世界観を表現し、印象に残す
・ 音声ナレーションとテキスト情報を連動させて内容の理解を促す
・ 重要なキーワードやメリットは画面中央や色付きで強調する
・ 映像内の情報量は多すぎず、簡潔で分かりやすい表現を心がける
また、製品の利用シーンや比較などを具体的に示すことで、視聴者は自分ごととして受け取りやすくなります。加えて、静止画や資料と連動させることで、訴求力の高い映像演出が実現できます。
展示会動画におけるこうした細部の工夫が、営業活動やその後のフォローの成果にも直結する要素となります。
展示会動画の制作費用と時間の目安
展示会動画を制作する際、多くの担当者が気にするのが費用と制作期間です。これらは、動画の種類や長さ、演出の複雑さ、素材の有無、そしてどのような制作会社に依頼するかによって大きく変動します。
一般的な目安としては以下の通りです。
・ シンプルな実写動画(1〜2分)
→約30〜50万円程度、制作期間:2〜3週間
・ アニメーションやCGを用いた動画(2〜3分)
→約50〜100万円程度、制作期間:3〜5週間
・ 複数のシーンやナレーション・BGM・テロップが含まれる本格動画
→約100万円以上、制作期間:1〜2ヶ月程度
これに加え、打ち合わせや企画立案、撮影場所の確保、機材の準備なども必要になる場合があります。そのため、スケジュールにはある程度の余裕を持つことが推奨されます。
また、再生環境や出力媒体(Web、SNS、展示会会場のモニターなど)によって、最適なデータ形式や仕様が異なるため、それに対応できる制作体制を持つパートナーの選定も重要です。
依頼から納品までの流れと効率的な作成方法
動画制作を効率よく進めるためには、依頼者側の準備と制作会社との連携がカギとなります。
以下は、一般的な制作の流れです。
1. ヒアリング・発注
目的、使用場所、予算、期間などを明確にしたうえで発注。
この時点で社内の意思統一がされていると、後の工程がスムーズになります。
2. 企画・構成の立案
コンセプト設定や構成案の作成、演出の方向性を決定。
必要に応じて参考事例を提示し、イメージのすり合わせを行います。
3. 撮影・作成
実写の場合は会場や人員の調整、アニメーションの場合はデザインや
動きの設計を行います。素材の準備や文字情報の提供も重要です。
4. 編集・仕上げ
ナレーションや音楽、字幕などを加え、最終的なクオリティ調整を行います。
5. 確認・納品
修正点の反映を経て、各媒体に合わせたデータで納品。
再生テストや配信方法の確認も行うと安心です。
特に短納期の場合は、初期段階でしっかりとチェック項目を明示し、必要な資料や画像などを早めに用意することで、人件費や修正工数の削減にもつながります。
事例から学ぶ成功する展示会動画の特徴
実際の展示会では、動画を活用して成功を収めている企業が数多く存在します。彼らに共通しているのは、ターゲットの関心を深く理解し、それに沿った演出や構成を採用していることです。また、他社との差別化を図るために、独自のブランドやコンセプトを映像で明確に打ち出している点も重要です。
たとえば、ある製造業の企業は、製品の内部構造や操作手順をアニメーションで表現し、従来のパンフレットでは伝わりにくかったポイントを可視化しました。結果として、展示会での営業活動がスムーズに進み、商談件数も大幅に増加したという実績があります。
また、IT企業の中には、ティザー広告的な役割を持たせた短編動画をSNSで事前に配信し、展示会当日の集客に成功した事例もあります。このように、展示会当日だけでなく、前後のプロモーションと組み合わせて動画を活用することが成果に直結するのです。
成功している事例の多くでは、ターゲット視点を意識した「課題提示→解決策→実績紹介」というストーリー構成が採用されており、視覚と聴覚の両面から訴求することによって、印象と理解の定着が図られています。
実績ある制作会社やクリエイターの活用方法
クオリティの高い展示会動画を制作するためには、信頼できる制作会社やクリエイターの存在が不可欠です。プロに依頼することで、構成や演出、編集の技術力だけでなく、業界や展示会に特化したノウハウを活かすことができます。
まず検討すべきは、過去の実績や事例を確認することです。特に同業種や同規模のイベントでの経験がある制作会社は、要望に合った提案をしてくれる可能性が高いです。また、無料相談や見積もり対応がある会社であれば、初めてでも安心して相談できます。
依頼前には、以下の点を整理しておくとスムーズです。
・ 伝えたいメッセージや製品の特徴
・ 想定する再生媒体(展示会会場、YouTube、Webサイトなど)
・ 映像の長さや使用したい音楽・ナレーションの有無
・ 希望する納期や予算
・ 競合との比較材料としての役割があるか
また、社内に動画制作の経験がない場合でも、制作会社が構成案やコンセプト立案からサポートしてくれることが多いため、安心して進めることが可能です。
制作会社の選び方と依頼時の注意点
展示会動画を成功に導くためには、どの制作会社に依頼するかが非常に重要なポイントです。魅力的な映像を作るには、単に技術が高いだけでなく、展示会という特殊なシーンへの理解や、マーケティングの視点を持った提案力が求められます。
まず、候補となる制作会社の実績や対応業界をチェックしましょう。特に、自社と近い業界やイベントでの制作経験がある会社であれば、より具体的で的確な提案を受けられる可能性が高まります。また、WebやSNSでの動画配信を視野に入れている場合、その対応実績も確認するとよいでしょう。
また、複数の会社に見積もりを取り、予算感や提案内容を比較することも欠かせません。ただし、価格だけで判断するのではなく、以下のような観点でも評価することが大切です。
・ 企画・構成段階での提案力
・ 担当者の対応スピードやコミュニケーションの質
・ 制作後の修正対応やサポート体制
・ 納期遵守の実績や進行管理能力
・ クオリティの安定性(過去の映像やテスト版で確認可能)
映像制作の依頼で失敗しないためのチェックポイント
動画制作を初めて外注する場合、認識のズレや進行トラブルが起きるケースもあります。失敗を防ぐには、依頼前・制作中・納品後の各フェーズで、以下のチェックポイントを押さえておくことが有効です。
依頼前
・ 何のための動画なのか(目的)を明確にする
・ 会場や媒体など、使用シーンを具体的に伝える
・ 必要な素材(ロゴ、画像、製品資料など)を事前に整理
制作中
・ 構成案やナレーション原稿は初期段階で共有・確認
・ 定期的な進捗報告を依頼し、方向性のブレを防ぐ
・ テロップや字幕の内容チェックを入念に行う(誤字脱字の回避)
納品前
・ 必ず再生チェックを複数端末で実施
・ 修正点は明確にリスト化し、優先度を付けて伝える
・ 納品形式(mp4、movなど)や画面サイズを最終確認
これらを徹底することで、人員や時間のロスを防ぎ、効率よくクオリティの高い動画を完成させることができます。
まとめ:展示会動画で自社の魅力を最大限に伝えるために
展示会動画は、来場者に向けて短時間で強い印象を与え、自社の製品やサービスの魅力を最大限に訴求する手段として非常に有効です。映像ならではの表現力を活かすことで、他社ブースとの差別化や記憶に残るプレゼンテーションが実現できます。
成功するためには、目的を明確にし、視聴者のニーズや行動を見据えた構成を設計することが重要です。テロップや音響などの細かな演出も含めて、視覚と聴覚の両面から情報を伝えることで、理解と関心を深めることができます。
また、信頼できる制作会社や経験豊富なクリエイターと連携することで、より高いクオリティの映像制作が可能になります。費用や時間に配慮しつつも、効果的な設計と運用を行えば、展示会での集客力や商談化率を大きく高めることができるでしょう。
☞展示会動画で自社の魅力を引き出すために押さえるべきポイント
1. 出展目的の明確化
・ 新規顧客の獲得、商談の増加、ブランドのアピールなど、具体的な目標を設定
2. 効果的な展示会準備
・ スケジュール管理を徹底し、ブース設計・装飾・プロモーションを計画的に進める
3. 費用対効果を最大化
・ 補助金の活用、コスト削減の工夫を行い、限られた予算の中で最大の効果を目指す
4. 集客力のあるブース企画
・ ターゲットに合わせたデザインや展示物を活用し、来場者の興味を引く
5. プロモーションとマーケティング戦略の実施
・ SNS、Web、メールを活用した告知と、ノベルティなどの工夫で集客を促進
6. 展示会後のフォローアップと効果測定
・ 名刺やアンケートを整理し、リードを分類して適切なアプローチを行う
・ レポートを作成し、次回の展示会に向けた改善点を明確にする
映像は一度制作すれば展示会だけでなく、WebサイトやYouTube、SNSなど、さまざまな媒体でも活用できます。中長期的なマーケティング戦略の一環としても、その価値は非常に高いものです。
ぜひ、本記事で紹介したポイントや事例を参考に、自社に最適な展示会動画を企画・制作し、確実な成果につなげてください。